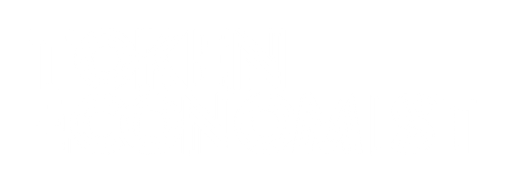暗号資産で“キャッシュレス生活”を完結させたい――その願いが最も難しい理由は、法定通貨への交換という大きな壁があるからです。$USDTを$BTCへ換え日本の取引所へ送金、さらに日本円へ戻すたびに失われる時間とスプレッド。そのようなプロセスを最も手軽にできる手段が、暗号資産デビットカードです。
本記事では、暗号資産デビットカードを選ぶポイントと共に、手数料が安くて日本居住者が使える3つのカードをピックアップします。
暗号資産デビットカードとは?
暗号資産デビットカードは、ウォレットに保有する$USDTなどの暗号資産を事前チャージし、VisaやMastercardのネットワーク経由でクレジットカードと同様に決済ができるデビットカードです。決済時にはカード残高から引き落としが行われ、現地通貨でそのまま支払うことができます。
暗号資産デビットカードは、カードの一番のメリットは、取引所が銀行口座へ資金を戻す手間・手数料を省ける点です。また、交換ルートを最小にできるため、日本居住者が抱える税務計算の面倒さを軽減することもできます。
暗号資産デビットカードを選ぶポイント5点
暗号資産デビットカードを選ぶ際の最重要指標は、大きく「発行可能国」「発行形態」「手数料」「チャージできる暗号資産」「その他特典」の5点があります。
発行可能国
発行可能国は、カード発行体のライセンス国や、発行体が採用しているカードのBIN(銀行識別番号)、その他発行体が準拠する規制で決まります。多くのカードでは、様々な地域の居住者が利用することができ、たとえ海外の発行体であっても日本の居住者が使えるものも存在しています。
発行形態
発行形態は「バーチャルカード」と「物理カード」に分類されます。
バーチャルカードは、カード番号のみが発行される形態です。バーチャルである分、発行手数料が安いことが大きなメリットです。物理的なカードではないため、原則的に実店舗で使うことができず、主にインターネット通販に適しています。バーチャルカードが Apple Pay や Google Pay に対応している場合、スマートフォンに紐づけて利用することができます。この場合、VisaやMastercardのタッチ決済に対応したカード決済端末がある実店舗で利用することができます。
物理カードは、一般的なクレジットカードと同様に、VisaやMastercardに対応した実店舗でも決済することができるカードです。物理的なカードである分、カード発行時に発行手数料が課されることが一般的です。また、多くの物理カードはATMで残高を引き出すことができる機能がついています。
手数料
手数料はカードによって種類が異なりますが、大まかに以下の手数料があります。
カード発行手数料
カードが発行される際に課される手数料です。バーチャルカードは無料の場合がありますが、物理カードでは数十ドル~500ドルが課されることが一般的です。発行体によって、一度きりの発行手数料の場合や、年間を徴収する場合があります。
決済手数料
決済にかかる手数料です。手数料はカード発行体によって異なり、1%程度が課されることが一般的です。また、多くのカードでは米ドルで残高を管理するため、日本で決済する場合は為替手数料も含まれます。
チャージ手数料
カード残高を暗号資産でチャージ(トップアップ)する際に課される手数料です。この手数料は、長期的に見た場合に実際に利用することができる額に大きく関わる要素です。カード発行体によって大きな開きがあり、0.1%から10%が課されます。
その他手数料
カード発行体によって、決済失敗時のペナルティの手数料を設けている場合があります。また、物理カードはATMから残高を引き出す際に手数料が課されます。
チャージできる暗号資産
多くのカードでは、チャージできる暗号資産として$USDTや$USDCといったステーブルコインに対応しています。また、一部のカードでは$BTCや$ETHなどの価格が変動するトークンにも対応しています。
その他特典
一部のカードでは、トークンによるポイント還元や、空港のラウンジ利用などの特典がついている場合があります。このような特典は、カードの額によってランク分けされている場合があるため、ご自身の利用想定額や生活スタイルに応じて検討する必要があります。
日本居住者でも使える暗号資産デビットカード4選
Tria Card
Tria Cardは、あらゆるチェーンに対応したウォレットを提供しているTriaプロジェクトにより提供されています。
カードは、自社ウォレットに統合される形で提供されています。核となるTriaウォレットの使い勝手は他社を圧倒しており、ガスレスによるトークン送信や、通常であれば承認処理が何度か必要なクロスチェーンスワップをワンクリックですることができます。これにより、カードにチャージするまでの導線が簡易になっています。
暗号資産デビットカードとしては珍しく、トークンによる利益還元機能が備わっており、決済された額に対して最大6%を受けとることができます。加えて、他のカードであれば通常であれば割引がかかる手数料を無料で提供しています。これらにより、結果的にこの手のカードとしては極めて良い交換レートを提供しています。加えて、物理カードの最上位モデルには空港ラウンジを格安で利用できる権利が付属されており、付加価値が際立っているカードでもあります。
※Tria Walletを登録すると詳細が確認できます。登録にはGoogleもしくはApple IDが必要です。
Cypher Card
Cypher Cardは、多くの国から発行することができるバーチャル/物理カードを提供しています。
チャージできる暗号資産の数は他社を圧倒しており、$USDCをはじめとして25以上のブロックチェーンに跨る500種類以上のトークンをチャージすることができます。また、手数料の低さに定評があり、年会費無料のStandardプランですら業界最安値水準を提供しています。
Cypher Cardでは、KYC完了後すぐにバーチャルカードが発行されます。また、Standardプランでは物理カードが無料で、送料として50ドルのみが請求されます。必要に応じて、メタルカードにアップグレードできる上位プランが用意されています。
Slash Card
Slash Cardは、初めて日本法に準拠した唯一の暗号資産デビットカードです。MetaMaskのようなセルフカストディ型ウォレットと連携し、保有している$USDCを即座に決済することができます。
一番の強みは、日本法に準拠している点です。海外法により発行された他社カードの場合、日本国内の決済システムで決済ができない場合がありますが、Slash Cardではそのようなことはありません。複数チェーンから直接チャージでき、バーチャル/物理カードが用意されます。また、Apple Pay等モバイル決済にも対応予定で、紹介報酬や利用額に連動したトークン還元が得られるのも魅力な点です。
残高は常に$USDC表示されるため価格変動が把握しやすく税務計算が簡素化できます。KYC後、18歳以上の日本居住者なら無料登録ができ、カード発行費用のみ別途発生します。NFT購入やSlashエコシステム上のDeFi利用と連動した追加特典が拡充されていく予定で、暗号資産の自由度と既存決済ネットワークの利便性を両立する次世代カードとして注目されています。