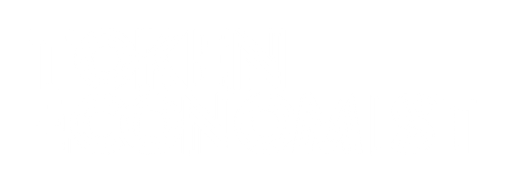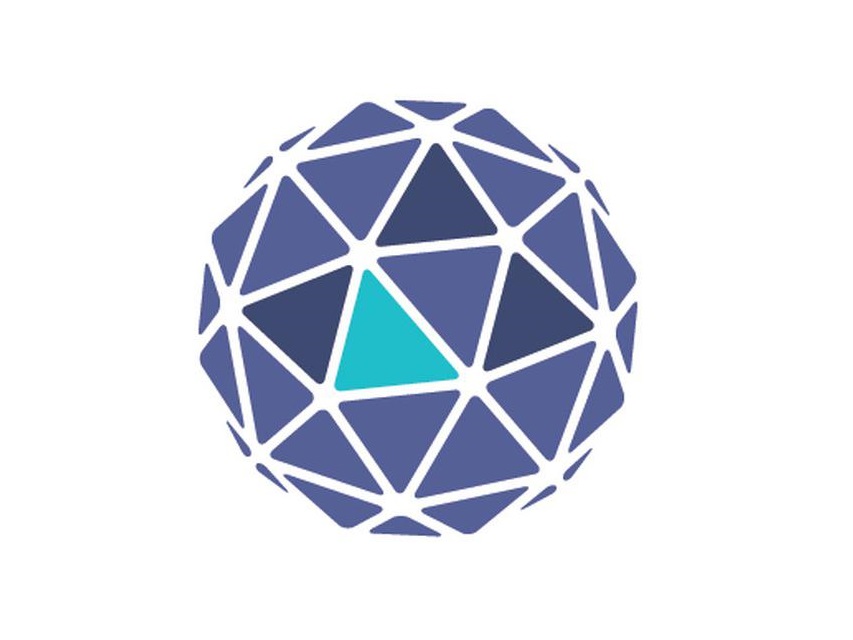私はブログでICOを頻繁にブログで取り上げているので、ブログを見せた時の質問で「良いICOは何?」というのをよく聞かれます。
過去に出した記事の指標に基づき、悪いものを弾いていくととだいたい良いものが残りますが、もう少し掘り下げてみたいと思います。
過去記事はこちら↓
トークンの種類を確認する
[the_ad id=”7860″]
まずは念のため言葉の定義を確認しておきます。
ICOで発行されるトークンは、大きくは2種類あります。ユーティリティトークンとセキュリティトークンです。
ユーティリティトークンはそのサービスにおいてお金のような役割をします。
ユーティリティトークンをポイントシステムに例えると、Tポイントが一番分かりやすいかもしれません。Tポイントは、Tポイントシステムを導入した店舗のみで使うことができます。当然ですが、Tポイントシステムを導入していない店舗では使うことができません。
Tポイントのように、お金のような役割をしてサービスを受けられる範囲が限られているのがユーティリティトークンです。
今回扱うテーマではありませんが、セキュリティトークンはセキュリティ(証券)の役割をするものになります。例えばセキュリティトークン保有者に事業の配当が支払われたりします。
純粋なセキュリティトークンは、それ自体はサービス利用のために使うことはできず、単に権利を証明するものになります。ただし、証券の法律に関わる分野になってくるため、現状は発行が難しい状態にあります。
また、取引所トークンに代表されるように、配当を出すけれども取引所サービスの支払いにも使えるようなユーティリティトークンとセキュリティトークンの両方の性格を持ち合わせたトークンも存在します。
今回扱うテーマはユーティリティトークンということを念頭に、続きをお読みください。
ユーティリティトークンの価値の公式
ユーティリティトークンの価値を算出する公式は、一般的に以下が使われています。
M = P * Q / V
- M = トークンの時価総額
- P = サービス価格
- Q = サービス利用回数
- V = 流通速度
個別に見ていきましょう。
Mはトークンの時価総額になります。トークンの発行数にもよりますが、時価総額が大きいトークンはトークン価格が高い傾向にあります。そのため、Mが大きくなればなるほどトークン価格は上がると解釈できます。
Pはサービス価格、Qはサービス利用回数です。分子が大きければ全体の値が大きくなるので、この2つが大きければ大きいほどMが大きくなる、つまりトークン価格が上がると解釈できます。
Vは流通速度です。どれくらいトークンが回転するのか、とれくらい支払いサイクルがあるのかになります。分母が小さければ全体の値が大きくなるので、Vが小さければ小さいほどMが大きくなる、つまりトークン価格が上がると解釈できます。
ここからは単純に算数です。公式における分子が大きくなって、分母が小さくなるものを見つければ良いわけです。
さらに言い換えると、みんなが大量の額を利用するけれども、そのトークンを簡単に手放そうとしないものを見つければ良いということになります。
[the_ad id=”7916″]
ユーティリティトークンの価値の公式から上がりそうなトークン分野を推定する
あとは少しアタマを使って、そのジャンルが「みんなが大量の額を利用するけれども、そのトークンを簡単に手放そうとしない」ものを推定していくだけです。
今回は極端な例を3つ取り上げてみます。人によって判断する感覚が違うところがあるため、あくまでも筆者の目線ということでご覧ください。
事例1:○○を支援する投げ銭プラットフォーム
国産トークンによくみられるパターンです。投げ銭をイメージしづらい方は、現実の募金のような寄付をイメージしてみると良いでしょう。
- P(サービス価格):投げ銭は少額な場合が多い。
⇒かなり小さい - Q(サービス利用回数):投げ銭を頻繁にすることは一般的に少ない。
⇒かなり小さい - V(流通速度):投げ銭用トークンを頻繁に調達することは少ない。
⇒小さい
投げ銭の場合は、決済する金額が他のサービスと比べると圧倒的に少ないと推定されるため。PQは相当小さい値に収まると推定されます。つまり、PQ/Vの値は小さくなると考えられます。
投資対象として捉える場合、避けた方が無難な分野といえます。
事例2:配当付きの取引所トークン
中国資本の取引所でよくみられるパターンです。
- P(サービス価格):他のトークンの購入に使われるため、一回の取引額が大きい。
⇒かなり大きい - Q(サービス利用回数):他のトークン購入に使えるようにするなど、利用されやすいようになっている。
⇒かなり大きい - V(流通速度):配当が出るため、投資家が手放しにくいようになっている。
⇒かなり小さい
取引所の場合は、お金そのものの取引が行われる場所になります。そのため、PQは事例1と比べると確実に大きいものになります。つまり、PQ/Vの値は大きくなると考えられます。
投資対象として捉える場合、望ましい分野であるといえます。
ちなみに、配当を出さない取引所になると、Vが大きくなる可能性があります。配当が出るところより不利になると想定されます。
事例3:プラットフォームの基軸通貨(BTC、ETHやNEOのような)
Bitcoin、EthereumやNEOのようなパターンです。
- P(サービス価格):マネーロンダリングに使われるくらい利用されている。
⇒かなり大きい - Q(サービス利用回数):多くの取引所が売買できるようにし、ICOの購入などにも使える。
⇒かなり大きい - V(流通速度):この分野のトークンを持っておくと、色々な支払いに利用できるため、ある程度の量を保有しておく。
⇒小さい
プラットフォームの基軸通貨の場合、利用用途が広範囲であるためPQに関しては、他のサービスと比べても圧倒的に大きくなります。
そして、たくさんの用途に使えるとなると、多くの人がその通貨を保有しておこうとなるためVは小さくなります。
投資対象として捉える場合、望ましい分野であるといえます。
ただし、この手のICOはメインネットの稼働前にとりあえずERC20でトークンを発行しておく場合が多いため、その段階だと価格が伸びない可能性があることを想定に入れる必要があります。
まとめ
このように「みんなが大量の額を利用するのか?」「そのトークンを簡単に手放そうとしないのか?」ということを少し考えるだけで、そのICOが将来的に上がる可能性が高いかどうかを推測することができます。
もちろん、必ず公式通りになるということではないので、あくまでも指標の1つという点で捉えておくと良いでしょう。
[the_ad id=”7916″]