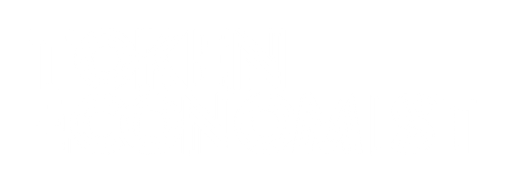DeFiの世界では、利回りを追求するさまざまな製品が登場しています。インデックス型商品はその代表的な例ですが、その多くが暗号資産の価格に追従したものになっています。しかし、LOCKONは一線を画したアプローチを採用し、高いパフォーマンスを示すウォレットをインデックス化することで、新たな価値創造に挑戦しています。
本インタビューでは、LOCKON(解説記事)のFounder & CEOである窪田昌弘氏に、この独自のアプローチやその背景にある想いについて伺いました。
LOCKONを始めた背景
加藤:LOCKONは、ほかのDeFi製品と比べてもかなりユニークですよね。今の形に行き着いた背景って、どういうところにあるんでしょう?
窪田氏:実はもともと私自身、為替のトレーダーやクリプトのBotトレーダーをやっていました。ただ、専門のクオンツチームや大量の予算があるわけでもなかったので、普通にやっていても規模や知見の面で限界を感じていました。そのような中、ブロックチェーン特有の「他社の取引履歴をオンチェーンで閲覧・分析できる」という点にすごく可能性を感じました。
「自分より優秀な人がいっぱいいるんだったら、その人たちのトレードを分析して、いいストラテジーを取り出せばいいじゃないか」という発想が、LOCKONを作るきっかけになったんです。
LOCKONとは?
加藤:LOCKONって、どのようなプロダクトなのでしょうか? 同種サービスと比べた時の強みはありますか?
窪田氏:LOCKONは、ブロックチェーン上のウォレットアドレスごとのトレードや利益の推移を分析して、「長期的に利益を出しながらリスクヘッジもできているウォレット」を探し出しています。そして、それらウォレットの戦略に連動したインデックストークンを発行して、保有者がその恩恵を受けられるようにする、というDeFiプロトコルです。
加藤:なるほど、オンチェーンで優秀なトレーダーをコピートレードしているイメージに近いのですね。
窪田氏:その通りです。似たプロダクトとしては、Index Coopさんがあります。ただ、Index Coopは「BTC50%・ETH50%」といった形で固定の配分を決めて自動購入する、いわゆる普通のインデックスです。一方でLOCKONは、参照しているウォレットアドレスのトレードをベースにして、ポートフォリオの割合を分単位でリバランスします。プロトコルやプロジェクト側が押し付けで方針を決めるのではなく、オンチェーンの実際の動きを参照している点が大きな違いです。
LOCKONのアドレス収集技術
加藤:LOCKONは、オンチェーンのアドレスを絞り込みながら優秀なアドレスを見つけていますが、とはいえ、10億件を超えるアドレスをフィルタリングするのはかなり大変そうに思います。どのような工夫をしているのでしょうか?
窪田氏:対象となるウォレットアドレスは10億以上あって、それぞれ数百から数十万のトランザクションがあります。全体を掛け合わせて分析するとなると、ものすごいサーバーリクエスト数になります。そこで、効率的に分析できるアルゴリズムを開発・実装していて、その点をAlchemyからも評価いただいて助成金をもらっています。大きなデータをスピーディかつ正確に扱うところが技術的な肝です。
LOCKONの今後
加藤:LOCKONはプロダクトとして既に成熟している印象を受けるのですが、今後のロードマップではどのようなことを考えていますか?
窪田氏:今後は、LOCKONが持つ分析プロトコルやアルゴリズムをヘッジファンド向けに使ってもらったり、Web2で発行されているポイントの運用に活用したり、日本向けのレンディング事業を展開したり……といった広がりを考えています。LOCKONはあくまでコア技術の一角なので、これを応用していろいろなサービス展開をしていくイメージですね。
加藤:1つのプロダクトにこだわらず、LOCKONをベースに派生させていくのですね。